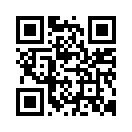【札幌LRTの会】 ~札幌の市電・路面電車と公共交通~ › 札幌市電の活用方策/延伸問題 › 【札幌市電 路線延伸の提案】 〜よくあるご質問(改訂版)〜
2006年01月19日
【札幌市電 路線延伸の提案】 〜よくあるご質問(改訂版)〜
皆様から寄せられた沢山のご意見、ご質問を取りまとめて、当会の見解とともに公式サイトにて公開致しました。>>こちらからどうぞ
ani.gif)
路線の在り方や議論の進め方、それに延伸に慎重な方々からの様々なご指摘など、取りまとめの過程において私達自身、自らの提案内容を見詰め直す良い機会になった気がします。ぜひ一度御覧になって、私達と一緒に考えてみて頂ければ幸いです。
■ 1.基本的なご質問
【Q1.1】 今なぜ路面電車を伸ばすの?
【Q1.2】 延長先はなぜJR札幌駅なの?
【Q1.3】 地下鉄があるのになぜ路面電車なの?
【Q1.4】 費用のあまり掛からないバスではなぜダメなの?
【Q1.5】 路線ループ化案は、どうなったの?
■ 2.路線・停留場について
【Q2.1】 路線案の実線と点線の違いは?
【Q2.2】 停留所がすこし多すぎない?
【Q2.3】 JR札幌駅ではどこから乗れるの?
■ 3.施設・経営の在り方について
【Q3.1】 運賃体系や収支見通しはどうなの?
【Q3.2】 仮に駅前通りに市電を通す場合、街路樹は撤去しなければならないのですか?
【Q3.3】 既存の車両は全て置き換えるのですか?
【Q3.4】 延伸区間の除雪等、冬対策は大丈夫?
【Q3.5】 市電存続には90億円の投資が必要と聞きましたが?
【Q3.6】 延伸にいくら掛かるの?
■ 4.議論の進め方について
【Q4.1】 なぜ延長案が3つもあるの?
【Q4.2】 札幌市が路線案を作っているのに、何故わざわざ別の案を出すの?
【Q4.3】 他の市民団体も既に路線延伸の提案を公表しています。敢えて別々の提案をするよりも、話し合って「統一案」を出してはどうでしょう?
【Q4.4】 経営形態の見直しなど課題は沢山あるのに、延伸議論だけを進めてしまって良いのでしょうか?
【Q4.5】 市電だけに捉われることなく、地下鉄、バス、自家用車も含めた総合的な交通体系を考えるべきでしょう?
■ 5.さまざまなご意見
【Q5.1】 路面電車にこだわらず、ガイドウェイバスやトロリーバス、新交通システムの導入も検討してみては?
【Q5.2】 サッポロファクトリーを経由して、新しい商業施設ができた苗穂方面にも延伸してはどうでしょう?
【Q5.3】 バッテリー式の「架線レス電車」を導入すれば建設コストを抑えられるのでは?
【Q5.4】 「都心のまちづくり」が目的なら、既存路線と繋げる必要は無いのでは?
■ 6.延伸反対・慎重派より
【Q6.1】 わざわざ延伸してまで市電を残す必要があるの?
【Q6.2】 市・交通局の財政では延伸は無理なのでは?
【Q6.3】 クルマの邪魔。都心部に路面電車は要りません!
【Q6.4】 地下歩行空間ができればJR札幌駅前〜大通間を快適に移動できるようになるので、敢えて市電を延伸する必要は無いのでは?
【Q6.5】 愛着や想い入れだけでは存続は無理でしょう?
【Q6.6】 山鼻地区の人にとっては便利になるかも知れませんが、市民全体にとってはメリットが無いのでは?
【Q6.7】 市電延伸がバス会社の経営を圧迫することにはなりませんか?
【Q6.8】 冬場は雪の影響を受けない地下鉄や地下歩道の方が便利なので、市電を利用する人はいないのでは?
ani.gif)
路線の在り方や議論の進め方、それに延伸に慎重な方々からの様々なご指摘など、取りまとめの過程において私達自身、自らの提案内容を見詰め直す良い機会になった気がします。ぜひ一度御覧になって、私達と一緒に考えてみて頂ければ幸いです。
■ 1.基本的なご質問
【Q1.1】 今なぜ路面電車を伸ばすの?
【Q1.2】 延長先はなぜJR札幌駅なの?
【Q1.3】 地下鉄があるのになぜ路面電車なの?
【Q1.4】 費用のあまり掛からないバスではなぜダメなの?
【Q1.5】 路線ループ化案は、どうなったの?
■ 2.路線・停留場について
【Q2.1】 路線案の実線と点線の違いは?
【Q2.2】 停留所がすこし多すぎない?
【Q2.3】 JR札幌駅ではどこから乗れるの?
■ 3.施設・経営の在り方について
【Q3.1】 運賃体系や収支見通しはどうなの?
【Q3.2】 仮に駅前通りに市電を通す場合、街路樹は撤去しなければならないのですか?
【Q3.3】 既存の車両は全て置き換えるのですか?
【Q3.4】 延伸区間の除雪等、冬対策は大丈夫?
【Q3.5】 市電存続には90億円の投資が必要と聞きましたが?
【Q3.6】 延伸にいくら掛かるの?
■ 4.議論の進め方について
【Q4.1】 なぜ延長案が3つもあるの?
【Q4.2】 札幌市が路線案を作っているのに、何故わざわざ別の案を出すの?
【Q4.3】 他の市民団体も既に路線延伸の提案を公表しています。敢えて別々の提案をするよりも、話し合って「統一案」を出してはどうでしょう?
【Q4.4】 経営形態の見直しなど課題は沢山あるのに、延伸議論だけを進めてしまって良いのでしょうか?
【Q4.5】 市電だけに捉われることなく、地下鉄、バス、自家用車も含めた総合的な交通体系を考えるべきでしょう?
■ 5.さまざまなご意見
【Q5.1】 路面電車にこだわらず、ガイドウェイバスやトロリーバス、新交通システムの導入も検討してみては?
【Q5.2】 サッポロファクトリーを経由して、新しい商業施設ができた苗穂方面にも延伸してはどうでしょう?
【Q5.3】 バッテリー式の「架線レス電車」を導入すれば建設コストを抑えられるのでは?
【Q5.4】 「都心のまちづくり」が目的なら、既存路線と繋げる必要は無いのでは?
■ 6.延伸反対・慎重派より
【Q6.1】 わざわざ延伸してまで市電を残す必要があるの?
【Q6.2】 市・交通局の財政では延伸は無理なのでは?
【Q6.3】 クルマの邪魔。都心部に路面電車は要りません!
【Q6.4】 地下歩行空間ができればJR札幌駅前〜大通間を快適に移動できるようになるので、敢えて市電を延伸する必要は無いのでは?
【Q6.5】 愛着や想い入れだけでは存続は無理でしょう?
【Q6.6】 山鼻地区の人にとっては便利になるかも知れませんが、市民全体にとってはメリットが無いのでは?
【Q6.7】 市電延伸がバス会社の経営を圧迫することにはなりませんか?
【Q6.8】 冬場は雪の影響を受けない地下鉄や地下歩道の方が便利なので、市電を利用する人はいないのでは?
【札幌市電】「ループ化」工事スケジュールの報道
【札幌市電】「広報さっぽろ」2012年6月号・路面電車特集
【札幌市電】「路面電車活用計画(案)」配布中
【札幌市電】上下分離・民間委託検討へ
【札幌市電】「ループ化」延伸ルートの現状
【札幌市】市長記者会見記録(市電ループ化・低床車両関連)
【札幌市電】「広報さっぽろ」2012年6月号・路面電車特集
【札幌市電】「路面電車活用計画(案)」配布中
【札幌市電】上下分離・民間委託検討へ
【札幌市電】「ループ化」延伸ルートの現状
【札幌市】市長記者会見記録(市電ループ化・低床車両関連)
Posted by 札幌LRTの会 at 16:24
│札幌市電の活用方策/延伸問題
この記事へのコメント
お疲れ様です。
痒い所まで手が届くQ&Aになっていると思います。
これだけ質問・意見があるというのは、とても良い傾向ですよね。
新しい事への不安感はあって当然です。だからこそ、このQ&Aは必要だと思います。
痒い所まで手が届くQ&Aになっていると思います。
これだけ質問・意見があるというのは、とても良い傾向ですよね。
新しい事への不安感はあって当然です。だからこそ、このQ&Aは必要だと思います。
Posted by ゲスト at 2006年01月18日 00:24
佐々木さん、コメントありがとうございます。
市電延伸については賛否両論、さまざまな御意見があるのは承知していますが、情報発信というのは難しいもので、とかく一部のキーワードだけが本筋を離れて一人歩きしてしまいがちなものですから、私達もできるだけ丁寧に、慎重に御説明させて頂かねばと思っています。
まだまだ説明不足の点もあるかも知れませんが、これからも皆さんの声に耳を傾けながら、私達も更に勉強を重ねていきたいと思っています。
(札幌LRTの会・鈴木周作)
市電延伸については賛否両論、さまざまな御意見があるのは承知していますが、情報発信というのは難しいもので、とかく一部のキーワードだけが本筋を離れて一人歩きしてしまいがちなものですから、私達もできるだけ丁寧に、慎重に御説明させて頂かねばと思っています。
まだまだ説明不足の点もあるかも知れませんが、これからも皆さんの声に耳を傾けながら、私達も更に勉強を重ねていきたいと思っています。
(札幌LRTの会・鈴木周作)
Posted by 札幌LRTの会 at 2006年01月20日 15:37
鈴木さん、こんにちは。東京在住のひのぱんだと申します。ずっとブログを拝見しておりましたが、忙しくて書き込みができませんでした。今日、やっと初めての書き込みをします。そのためちょっと長文ですがお許しください。
私は「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」と信じています。それに適しているツールが市電(バスは定時性がない、地下鉄は中距離移動向き)だと思います。また低床トラムであれば、少子化(バリアフリー)・高齢化(バリアフリー、そして自分も含め誰もが運転免許を返納するときがくることを忘れてはなりません)対策になります。
市電の存廃・延伸について調べてみると、「市電で街中を移動して何が面白いのか?」という意見も多いように感じました。それは日本中の街に言えることですが、やはり大型駅ビルと大型郊外SCだけが元気で、小売に元気がないのが最大要因ではないかと思います(私の実家は東京で商売をしていたので、お店経営側から見てもそう思います)。
私はアイルランドとフィンランドに長期滞在した経験があります。ダブリン(アイルランドは北海道とほぼ同じ面積で405万人、首都ダブリンは人口115万人)を例にとると、多くの人がシティセンタへ働きに、あるいはショッピングに出かけます。巨大郊外型SCはいくつもありますが街の魅力はそれらにまったく負けていません。その理由は街に魅力ある商店や施設が多いからだと思います。おいしいもの、心地よい雰囲気、専門の知識、エンタテイメントなどを提供してくれる楽しい小売や広場がたくさんあるからです(昨年ついにトラムが復活したそうですが、郊外とシティセンタを結ぶのはバスと南北に走るたった1本の郊外電車だけという、ヨーロッパの首都の中でも非常に車依存度が高い社会です)。
例えば、東京でフードコートというと、ファストフードチェーン店が集まっているだけで、エネルギー補給以外に魅力がありません。ダブリンだとフードコート以外にフードマーケットがあります。マーケットは日曜日に広場で、青空の下で、おいしいもの(チョコやら生カキやら惣菜まで)をちょい食いできたりします。ごく普通のヨーロッパのフードマーケットです。それを目当てに観光客だけでなく地元の人も日曜日にシティセンタに出てきます。
大学近くには教育や語学関連の専門書店があったり、サブカルチャー系だけがあつまったアーケードがあったりと、街にしかないものはたくさんあります。
市電は「赤字経営」「税金で札幌市の一部のエリアの人にだけメリット」、ゆえに関心がないとか廃止してもよいという人の気持ちも、私は十分に理解できます。ならばその「中央区内をループしている現状+札幌駅までの延伸」をフルに利用することから始めてはどうかなと私は思います。
魅力ある小売や施設、公共施設(または窓口)などにもっと沿線近くに来てもらったらどうでしょうか。例えば社会人が通える大学のサテライト教室(例:市立大学が社会人への門戸を広げ、アフター5に科目履修がしやすいシステムをつくるとか)が電停のそばにあるとしたら、中央区近辺で働くすべての人にメリットがあるのではと思います。「6:00に退社して6:30には楽勝で教室にいる」という時間通りの行動も可能と考えます。
(ヨーロッパのどの都市も同様ですが)市内に点在する観光施設・娯楽施設に接続することこそ、バスに任せるべきだと思います。週末や観光シーズンだけ増便すればよいのですからそのほうが合理的です。ま定時性もあまり重要ではありません。
さらにベビーカー同伴者は運賃を無料にしたら、まちに出る人が増えると思います。(私もこどもがいますが)私のの周囲では、幼児の世話をする母親(または父親)の多くは、平日はベビーカーで近くの公園へ散歩をし、週末に夫婦一緒に車で町に出かけます。車なら荷物を持たなくてすみ、駅ビルや郊外SCへ直行すればそこにはエレベーターがあります。「家には車があるのだから、平日にわざわざお金を払って苦労をしてまで電車・バスに乗る理由はない」のです。ゆえに週末は道が混雑します。札幌もおそらく同じではないでしょうか。
そこで、楽にただで街中を移動できるなら、平日に市電を使う母(父)親も増えるのではないかと思います。「子供を持つ家庭にとって一番必要な支援はお金」という政府の調査結果もあります。「ベビーカー同伴で行きやすいお店」を調べて冊子やWEBを作っている方もいるくらいですから、平日に街に出られる母(父)親が増えれば地元への経済効果もあると思います。また「どこかで減税だったのに、何かの増税でチャラ」ということが多い税制優遇に比べて、「ベビーカー同伴者は無料」は目に見えるわかりやすい子育て支援ではないかと思います。
私は札幌へは毎年のように家族で行きますが、札幌は私が滞在したことがあるすべての都市の中でも、とても住みやすくて魅力のある都市だと思います(雪も含めて。雪は邪魔者ではなく魅力です)。もちろん、読売新聞北海道版や北海道新聞やウェブシティさっぽろなどから、住んでいる人にとっては解決して欲しい問題がたくさんあることも知っています。
東京で「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」を作ることは、人口が半減しても不可能だと私は思っています。でも札幌はそれができる土壌を持っていると感じます。東京オリンピック時に、「東京の自動車重視の交通政策は行き詰る。札幌は東京の真似をしないという予測から連接車導入と路線拡張を続けてきた」(鉄道ピクトリアル2006年1月増刊号 名鉄の特集記事より)と雑誌で読みました。その先見の明には脱帽です。
まったく関係ないことかもしれませんが、中央が国公立大学を統廃合している今、札幌市が市立大学を新設する決断をしたことにも私は驚かされました。日本は「格差社会」になりつつあるといわれますが、これから一番格差が広がるのは、高等教育を受けられる人と受けらない人の差だと思います。ゆえに教育の機会均等は国が責任を持つべきと私は信じています。「(簡単にはいかないが、良いことならもがきながら)中央ができないことを北海道はやっている」 そう感じます。
市電存続に反対・保留の人も、「魅力あるまち」のためのアイディアを出し合うことが必要と思います。それらをこねてもんで、時には社会実験をして体験をしてもらう。その中で「既存の市電が活用できるんじゃない?!」という意見が多くなればいいなと、私は思います。
PS:雪の中、元円山公園電停に停車している連接車の絵はすてきですね。ポストカードにはないようですので、PCの壁紙にさせていただいています。
私は「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」と信じています。それに適しているツールが市電(バスは定時性がない、地下鉄は中距離移動向き)だと思います。また低床トラムであれば、少子化(バリアフリー)・高齢化(バリアフリー、そして自分も含め誰もが運転免許を返納するときがくることを忘れてはなりません)対策になります。
市電の存廃・延伸について調べてみると、「市電で街中を移動して何が面白いのか?」という意見も多いように感じました。それは日本中の街に言えることですが、やはり大型駅ビルと大型郊外SCだけが元気で、小売に元気がないのが最大要因ではないかと思います(私の実家は東京で商売をしていたので、お店経営側から見てもそう思います)。
私はアイルランドとフィンランドに長期滞在した経験があります。ダブリン(アイルランドは北海道とほぼ同じ面積で405万人、首都ダブリンは人口115万人)を例にとると、多くの人がシティセンタへ働きに、あるいはショッピングに出かけます。巨大郊外型SCはいくつもありますが街の魅力はそれらにまったく負けていません。その理由は街に魅力ある商店や施設が多いからだと思います。おいしいもの、心地よい雰囲気、専門の知識、エンタテイメントなどを提供してくれる楽しい小売や広場がたくさんあるからです(昨年ついにトラムが復活したそうですが、郊外とシティセンタを結ぶのはバスと南北に走るたった1本の郊外電車だけという、ヨーロッパの首都の中でも非常に車依存度が高い社会です)。
例えば、東京でフードコートというと、ファストフードチェーン店が集まっているだけで、エネルギー補給以外に魅力がありません。ダブリンだとフードコート以外にフードマーケットがあります。マーケットは日曜日に広場で、青空の下で、おいしいもの(チョコやら生カキやら惣菜まで)をちょい食いできたりします。ごく普通のヨーロッパのフードマーケットです。それを目当てに観光客だけでなく地元の人も日曜日にシティセンタに出てきます。
大学近くには教育や語学関連の専門書店があったり、サブカルチャー系だけがあつまったアーケードがあったりと、街にしかないものはたくさんあります。
市電は「赤字経営」「税金で札幌市の一部のエリアの人にだけメリット」、ゆえに関心がないとか廃止してもよいという人の気持ちも、私は十分に理解できます。ならばその「中央区内をループしている現状+札幌駅までの延伸」をフルに利用することから始めてはどうかなと私は思います。
魅力ある小売や施設、公共施設(または窓口)などにもっと沿線近くに来てもらったらどうでしょうか。例えば社会人が通える大学のサテライト教室(例:市立大学が社会人への門戸を広げ、アフター5に科目履修がしやすいシステムをつくるとか)が電停のそばにあるとしたら、中央区近辺で働くすべての人にメリットがあるのではと思います。「6:00に退社して6:30には楽勝で教室にいる」という時間通りの行動も可能と考えます。
(ヨーロッパのどの都市も同様ですが)市内に点在する観光施設・娯楽施設に接続することこそ、バスに任せるべきだと思います。週末や観光シーズンだけ増便すればよいのですからそのほうが合理的です。ま定時性もあまり重要ではありません。
さらにベビーカー同伴者は運賃を無料にしたら、まちに出る人が増えると思います。(私もこどもがいますが)私のの周囲では、幼児の世話をする母親(または父親)の多くは、平日はベビーカーで近くの公園へ散歩をし、週末に夫婦一緒に車で町に出かけます。車なら荷物を持たなくてすみ、駅ビルや郊外SCへ直行すればそこにはエレベーターがあります。「家には車があるのだから、平日にわざわざお金を払って苦労をしてまで電車・バスに乗る理由はない」のです。ゆえに週末は道が混雑します。札幌もおそらく同じではないでしょうか。
そこで、楽にただで街中を移動できるなら、平日に市電を使う母(父)親も増えるのではないかと思います。「子供を持つ家庭にとって一番必要な支援はお金」という政府の調査結果もあります。「ベビーカー同伴で行きやすいお店」を調べて冊子やWEBを作っている方もいるくらいですから、平日に街に出られる母(父)親が増えれば地元への経済効果もあると思います。また「どこかで減税だったのに、何かの増税でチャラ」ということが多い税制優遇に比べて、「ベビーカー同伴者は無料」は目に見えるわかりやすい子育て支援ではないかと思います。
私は札幌へは毎年のように家族で行きますが、札幌は私が滞在したことがあるすべての都市の中でも、とても住みやすくて魅力のある都市だと思います(雪も含めて。雪は邪魔者ではなく魅力です)。もちろん、読売新聞北海道版や北海道新聞やウェブシティさっぽろなどから、住んでいる人にとっては解決して欲しい問題がたくさんあることも知っています。
東京で「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」を作ることは、人口が半減しても不可能だと私は思っています。でも札幌はそれができる土壌を持っていると感じます。東京オリンピック時に、「東京の自動車重視の交通政策は行き詰る。札幌は東京の真似をしないという予測から連接車導入と路線拡張を続けてきた」(鉄道ピクトリアル2006年1月増刊号 名鉄の特集記事より)と雑誌で読みました。その先見の明には脱帽です。
まったく関係ないことかもしれませんが、中央が国公立大学を統廃合している今、札幌市が市立大学を新設する決断をしたことにも私は驚かされました。日本は「格差社会」になりつつあるといわれますが、これから一番格差が広がるのは、高等教育を受けられる人と受けらない人の差だと思います。ゆえに教育の機会均等は国が責任を持つべきと私は信じています。「(簡単にはいかないが、良いことならもがきながら)中央ができないことを北海道はやっている」 そう感じます。
市電存続に反対・保留の人も、「魅力あるまち」のためのアイディアを出し合うことが必要と思います。それらをこねてもんで、時には社会実験をして体験をしてもらう。その中で「既存の市電が活用できるんじゃない?!」という意見が多くなればいいなと、私は思います。
PS:雪の中、元円山公園電停に停車している連接車の絵はすてきですね。ポストカードにはないようですので、PCの壁紙にさせていただいています。
Posted by ゲスト at 2006年01月26日 00:36
鈴木さん、こんにちは。東京在住のひのぱんだと申します。ずっとブログを拝見しておりましたが、忙しくて書き込みができませんでした。今日、やっと初めての書き込みをします。そのためちょっと長文ですがお許しください。
私は「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」と信じています。それに適しているツールが市電(バスは定時性がない、地下鉄は中距離移動向き)だと思います。また低床トラムであれば、少子化(バリアフリー)・高齢化(バリアフリー、そして自分も含め誰もが運転免許を返納するときがくることを忘れてはなりません)対策になります。
市電の存廃・延伸について調べてみると、「市電で街中を移動して何が面白いのか?」という意見も多いように感じました。それは日本中の街に言えることですが、やはり大型駅ビルと大型郊外SCだけが元気で、小売に元気がないのが最大要因ではないかと思います(私の実家は東京で商売をしていたので、お店経営側から見てもそう思います)。
私はアイルランドとフィンランドに長期滞在した経験があります。ダブリン(アイルランドは北海道とほぼ同じ面積で405万人、首都ダブリンは人口115万人)を例にとると、多くの人がシティセンタへ働きに、あるいはショッピングに出かけます。巨大郊外型SCはいくつもありますが街の魅力はそれらにまったく負けていません。その理由は街に魅力ある商店や施設が多いからだと思います。おいしいもの、心地よい雰囲気、専門の知識、エンタテイメントなどを提供してくれる楽しい小売や広場がたくさんあるからです(昨年ついにトラムが復活したそうですが、郊外とシティセンタを結ぶのはバスと南北に走るたった1本の郊外電車だけという、ヨーロッパの首都の中でも非常に車依存度が高い社会です)。
例えば、東京でフードコートというと、ファストフードチェーン店が集まっているだけで、エネルギー補給以外に魅力がありません。ダブリンだとフードコート以外にフードマーケットがあります。マーケットは日曜日に広場で、青空の下で、おいしいもの(チョコやら生カキやら惣菜まで)をちょい食いできたりします。ごく普通のヨーロッパのフードマーケットです。それを目当てに観光客だけでなく地元の人も日曜日にシティセンタに出てきます。
大学近くには教育や語学関連の専門書店があったり、サブカルチャー系だけがあつまったアーケードがあったりと、街にしかないものはたくさんあります。
市電は「赤字経営」「税金で札幌市の一部のエリアの人にだけメリット」、ゆえに関心がないとか廃止してもよいという人の気持ちも、私は十分に理解できます。ならばその「中央区内をループしている現状+札幌駅までの延伸」をフルに利用することから始めてはどうかなと私は思います。
魅力ある小売や施設、公共施設(または窓口)などにもっと沿線近くに来てもらったらどうでしょうか。例えば社会人が通える大学のサテライト教室(例:市立大学が社会人への門戸を広げ、アフター5に科目履修がしやすいシステムをつくるとか)が電停のそばにあるとしたら、中央区近辺で働くすべての人にメリットがあるのではと思います。「6:00に退社して6:30には楽勝で教室にいる」という時間通りの行動も可能と考えます。
(ヨーロッパのどの都市も同様ですが)市内に点在する観光施設・娯楽施設に接続することこそ、バスに任せるべきだと思います。週末や観光シーズンだけ増便すればよいのですからそのほうが合理的です。ま定時性もあまり重要ではありません。
さらにベビーカー同伴者は運賃を無料にしたら、まちに出る人が増えると思います。(私もこどもがいますが)私のの周囲では、幼児の世話をする母親(または父親)の多くは、平日はベビーカーで近くの公園へ散歩をし、週末に夫婦一緒に車で町に出かけます。車なら荷物を持たなくてすみ、駅ビルや郊外SCへ直行すればそこにはエレベーターがあります。「家には車があるのだから、平日にわざわざお金を払って苦労をしてまで電車・バスに乗る理由はない」のです。ゆえに週末は道が混雑します。札幌もおそらく同じではないでしょうか。
そこで、楽にただで街中を移動できるなら、平日に市電を使う母(父)親も増えるのではないかと思います。「子供を持つ家庭にとって一番必要な支援はお金」という政府の調査結果もあります。「ベビーカー同伴で行きやすいお店」を調べて冊子やWEBを作っている方もいるくらいですから、平日に街に出られる母(父)親が増えれば地元への経済効果もあると思います。また「どこかで減税だったのに、何かの増税でチャラ」ということが多い税制優遇に比べて、「ベビーカー同伴者は無料」は目に見えるわかりやすい子育て支援ではないかと思います。
私は札幌へは毎年のように家族で行きますが、札幌は私が滞在したことがあるすべての都市の中でも、とても住みやすくて魅力のある都市だと思います(雪も含めて。雪は邪魔者ではなく魅力です)。もちろん、読売新聞北海道版や北海道新聞やウェブシティさっぽろなどから、住んでいる人にとっては解決して欲しい問題がたくさんあることも知っています。
東京で「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」を作ることは、人口が半減しても不可能だと私は思っています。でも札幌はそれができる土壌を持っていると感じます。東京オリンピック時に、「東京の自動車重視の交通政策は行き詰る。札幌は東京の真似をしないという予測から連接車導入と路線拡張を続けてきた」(鉄道ピクトリアル2006年1月増刊号 名鉄の特集記事より)と雑誌で読みました。その先見の明には脱帽です。
まったく関係ないことかもしれませんが、中央が国公立大学を統廃合している今、札幌市が市立大学を新設する決断をしたことにも私は驚かされました。日本は「格差社会」になりつつあるといわれますが、これから一番格差が広がるのは、高等教育を受けられる人と受けらない人の差だと思います。ゆえに教育の機会均等は国が責任を持つべきと私は信じています。「(簡単にはいかないが、良いことならもがきながら)中央ができないことを北海道はやっている」 そう感じます。
市電存続に反対・保留の人も、「魅力あるまち」のためのアイディアを出し合うことが必要と思います。それらをこねてもんで、時には社会実験をして体験をしてもらう。その中で「既存の市電が活用できるんじゃない?!」という意見が多くなればいいなと、私は思います。
PS:雪の中、元円山公園電停に停車している連接車の絵はすてきですね。ポストカードにはないようですので、PCの壁紙にさせていただいています。
私は「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」と信じています。それに適しているツールが市電(バスは定時性がない、地下鉄は中距離移動向き)だと思います。また低床トラムであれば、少子化(バリアフリー)・高齢化(バリアフリー、そして自分も含め誰もが運転免許を返納するときがくることを忘れてはなりません)対策になります。
市電の存廃・延伸について調べてみると、「市電で街中を移動して何が面白いのか?」という意見も多いように感じました。それは日本中の街に言えることですが、やはり大型駅ビルと大型郊外SCだけが元気で、小売に元気がないのが最大要因ではないかと思います(私の実家は東京で商売をしていたので、お店経営側から見てもそう思います)。
私はアイルランドとフィンランドに長期滞在した経験があります。ダブリン(アイルランドは北海道とほぼ同じ面積で405万人、首都ダブリンは人口115万人)を例にとると、多くの人がシティセンタへ働きに、あるいはショッピングに出かけます。巨大郊外型SCはいくつもありますが街の魅力はそれらにまったく負けていません。その理由は街に魅力ある商店や施設が多いからだと思います。おいしいもの、心地よい雰囲気、専門の知識、エンタテイメントなどを提供してくれる楽しい小売や広場がたくさんあるからです(昨年ついにトラムが復活したそうですが、郊外とシティセンタを結ぶのはバスと南北に走るたった1本の郊外電車だけという、ヨーロッパの首都の中でも非常に車依存度が高い社会です)。
例えば、東京でフードコートというと、ファストフードチェーン店が集まっているだけで、エネルギー補給以外に魅力がありません。ダブリンだとフードコート以外にフードマーケットがあります。マーケットは日曜日に広場で、青空の下で、おいしいもの(チョコやら生カキやら惣菜まで)をちょい食いできたりします。ごく普通のヨーロッパのフードマーケットです。それを目当てに観光客だけでなく地元の人も日曜日にシティセンタに出てきます。
大学近くには教育や語学関連の専門書店があったり、サブカルチャー系だけがあつまったアーケードがあったりと、街にしかないものはたくさんあります。
市電は「赤字経営」「税金で札幌市の一部のエリアの人にだけメリット」、ゆえに関心がないとか廃止してもよいという人の気持ちも、私は十分に理解できます。ならばその「中央区内をループしている現状+札幌駅までの延伸」をフルに利用することから始めてはどうかなと私は思います。
魅力ある小売や施設、公共施設(または窓口)などにもっと沿線近くに来てもらったらどうでしょうか。例えば社会人が通える大学のサテライト教室(例:市立大学が社会人への門戸を広げ、アフター5に科目履修がしやすいシステムをつくるとか)が電停のそばにあるとしたら、中央区近辺で働くすべての人にメリットがあるのではと思います。「6:00に退社して6:30には楽勝で教室にいる」という時間通りの行動も可能と考えます。
(ヨーロッパのどの都市も同様ですが)市内に点在する観光施設・娯楽施設に接続することこそ、バスに任せるべきだと思います。週末や観光シーズンだけ増便すればよいのですからそのほうが合理的です。ま定時性もあまり重要ではありません。
さらにベビーカー同伴者は運賃を無料にしたら、まちに出る人が増えると思います。(私もこどもがいますが)私のの周囲では、幼児の世話をする母親(または父親)の多くは、平日はベビーカーで近くの公園へ散歩をし、週末に夫婦一緒に車で町に出かけます。車なら荷物を持たなくてすみ、駅ビルや郊外SCへ直行すればそこにはエレベーターがあります。「家には車があるのだから、平日にわざわざお金を払って苦労をしてまで電車・バスに乗る理由はない」のです。ゆえに週末は道が混雑します。札幌もおそらく同じではないでしょうか。
そこで、楽にただで街中を移動できるなら、平日に市電を使う母(父)親も増えるのではないかと思います。「子供を持つ家庭にとって一番必要な支援はお金」という政府の調査結果もあります。「ベビーカー同伴で行きやすいお店」を調べて冊子やWEBを作っている方もいるくらいですから、平日に街に出られる母(父)親が増えれば地元への経済効果もあると思います。また「どこかで減税だったのに、何かの増税でチャラ」ということが多い税制優遇に比べて、「ベビーカー同伴者は無料」は目に見えるわかりやすい子育て支援ではないかと思います。
私は札幌へは毎年のように家族で行きますが、札幌は私が滞在したことがあるすべての都市の中でも、とても住みやすくて魅力のある都市だと思います(雪も含めて。雪は邪魔者ではなく魅力です)。もちろん、読売新聞北海道版や北海道新聞やウェブシティさっぽろなどから、住んでいる人にとっては解決して欲しい問題がたくさんあることも知っています。
東京で「まち歩きが楽しい街」=「魅力あるまち」を作ることは、人口が半減しても不可能だと私は思っています。でも札幌はそれができる土壌を持っていると感じます。東京オリンピック時に、「東京の自動車重視の交通政策は行き詰る。札幌は東京の真似をしないという予測から連接車導入と路線拡張を続けてきた」(鉄道ピクトリアル2006年1月増刊号 名鉄の特集記事より)と雑誌で読みました。その先見の明には脱帽です。
まったく関係ないことかもしれませんが、中央が国公立大学を統廃合している今、札幌市が市立大学を新設する決断をしたことにも私は驚かされました。日本は「格差社会」になりつつあるといわれますが、これから一番格差が広がるのは、高等教育を受けられる人と受けらない人の差だと思います。ゆえに教育の機会均等は国が責任を持つべきと私は信じています。「(簡単にはいかないが、良いことならもがきながら)中央ができないことを北海道はやっている」 そう感じます。
市電存続に反対・保留の人も、「魅力あるまち」のためのアイディアを出し合うことが必要と思います。それらをこねてもんで、時には社会実験をして体験をしてもらう。その中で「既存の市電が活用できるんじゃない?!」という意見が多くなればいいなと、私は思います。
PS:雪の中、元円山公園電停に停車している連接車の絵はすてきですね。ポストカードにはないようですので、PCの壁紙にさせていただいています。
Posted by ゲスト at 2006年01月26日 00:44
ひのぱんださん、コメントありがとうございます。
仰るとおり、単に市電を延ばすだけではなく、そこに魅力的な商業エリアが構築されてこそ意義があるものだと思います。
奇しくも先日の例会で私達のメンバーの間からも、「本当は市電延伸問題から考えるのではなく、まずは魅力的な“まちづくり”から始めるのが筋なんだけど・・・」という主旨の発言がありました。
市電をとりまく諸般の事情や、存廃問題から現在に至るまでの議論の経緯もあって、まずは市電という「ツール」を用意して、あとの“まちづくり”は沿道商業者の皆様に期待せざるを得ない・・・という現実に個人的には少々ジレンマも感じるところですが、とにかく、そういう観点だけはしっかりと肝に銘じて、まずは我々として出来ることから活動していかねばと思っています。
これからも「札幌LRTの会」の活動に暖かい御支援、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い致します。
(札幌LRTの会・鈴木周作)
仰るとおり、単に市電を延ばすだけではなく、そこに魅力的な商業エリアが構築されてこそ意義があるものだと思います。
奇しくも先日の例会で私達のメンバーの間からも、「本当は市電延伸問題から考えるのではなく、まずは魅力的な“まちづくり”から始めるのが筋なんだけど・・・」という主旨の発言がありました。
市電をとりまく諸般の事情や、存廃問題から現在に至るまでの議論の経緯もあって、まずは市電という「ツール」を用意して、あとの“まちづくり”は沿道商業者の皆様に期待せざるを得ない・・・という現実に個人的には少々ジレンマも感じるところですが、とにかく、そういう観点だけはしっかりと肝に銘じて、まずは我々として出来ることから活動していかねばと思っています。
これからも「札幌LRTの会」の活動に暖かい御支援、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い致します。
(札幌LRTの会・鈴木周作)
Posted by 札幌LRTの会 at 2006年01月27日 22:40

_01.gif) 【札幌LRTの会公式サイト】
【札幌LRTの会公式サイト】






_01.gif)